【本】「学校」を生きる人々のナラティヴ:子どもと教師・スクールカウンセラー・保護者の心のずれ【感想】
自己紹介等にも書いているように私自身が不登校を経験して生きてきたので不登校に関する本等をよく読みます。
そして何か自分で発信できないかと考えるのです。
Contents
「学校」を生きる人々のナラティヴ:子どもと教師・スクールカウンセラー・保護者の心のずれ
今年の6月にこちらの本が販売され、タイトルでピピッときました。
昨今学校での問題がニュースとなることが多いですが、子ども・保護者・教師・スクールカウンセラーそれぞれ考えていることが違うのではないかと思うのです。
本来は子ども中心であるべきですが自分の社会的に期待される役割を演じようとする保護者・教師によって不登校児童の認知がどんどん歪められているのではないかと。
この本ではその"溝"のようなものを実際の当事者の経験を含めて語られていてなるほどと思える点が多数ありました。
内容
子どもや教師・スクールカウンセラー・保護者にとって「学校」とはどのような場所か。一般的な言説の中で語られている「学校」と子どもや大人がそこで生きている現実の「学校」との間で、また子どもの思いと大人の思いとの間で、どのようなずれが生じているのか。本書は、子どもと大人、それぞれの立場・視点から生まれる多様な声・物語に着目し、元生徒と教師・スクールカウンセラーの語り合い等を通して、私たちが自明だと考えている学校についての認識を捉え直し、学校が抱える課題の本質や、学校がもつ可能性などについて考える。

【パニック障害・在宅勤務・副業】自宅で現役エンジニアから学べる TechAcademy [テックアカデミー]
自宅で現役エンジニアから学べるWeb制作・データサイエンス・AIなど幅広い分野に対応
10代〜40代の男女におすすめ!副業・フリーランス・就職/転職を目指す
挫折せずに学べる!初心者向けの副業コースが人気
現役プロのパーソナルメンターとの個別サポートで学びを加速!
ライフスタイルに合わせて受講できる!オンライン完結の TechAcademy でスキルアップ
普段の生活でポイントを貯めるならハピタス!
にほんブログ村

パニック障害ランキング

 https://panic-disorder-cure.com/self-introduction-detail/
https://panic-disorder-cure.com/self-introduction-detail/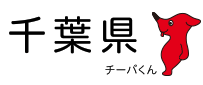
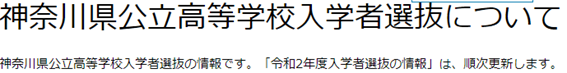
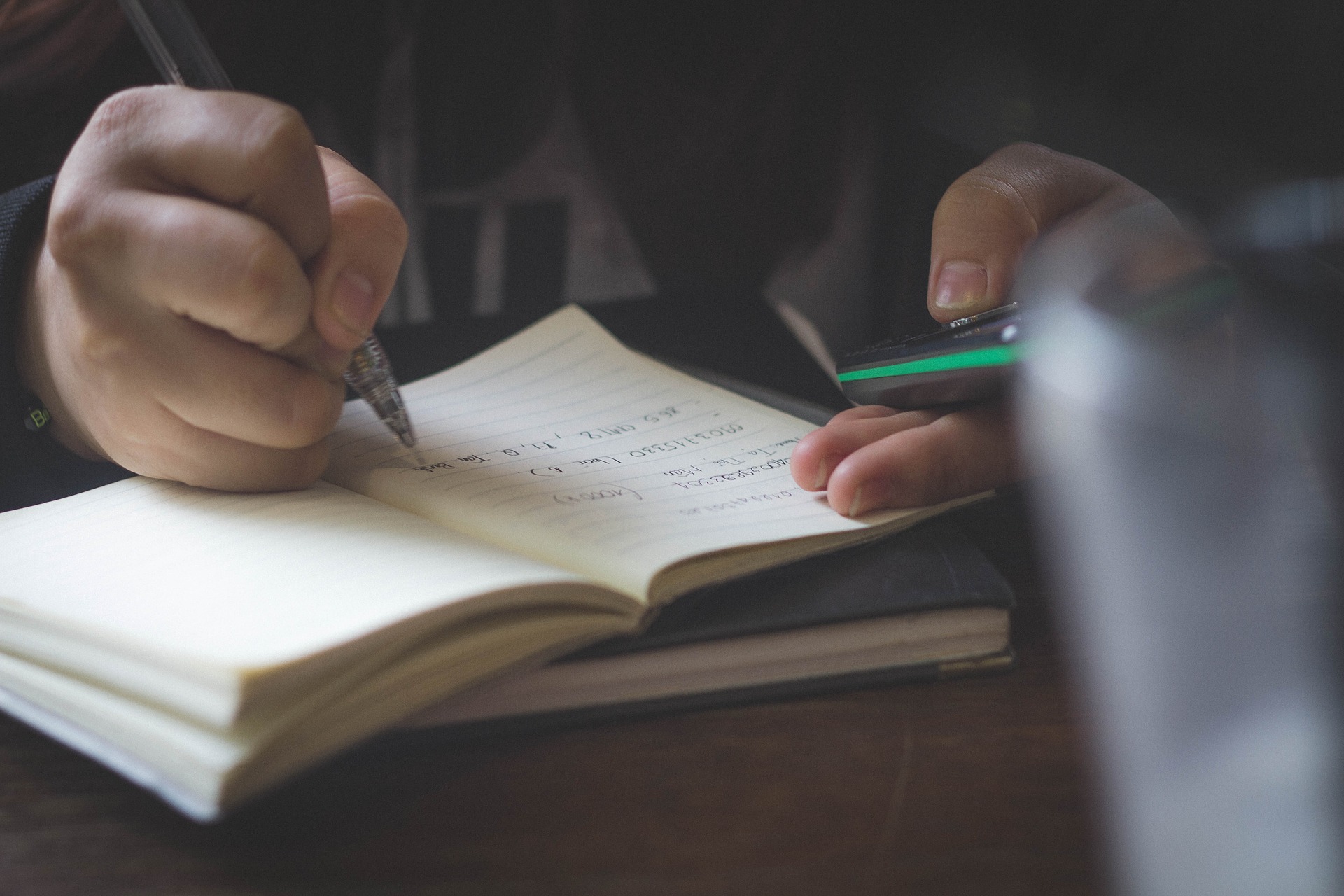
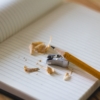

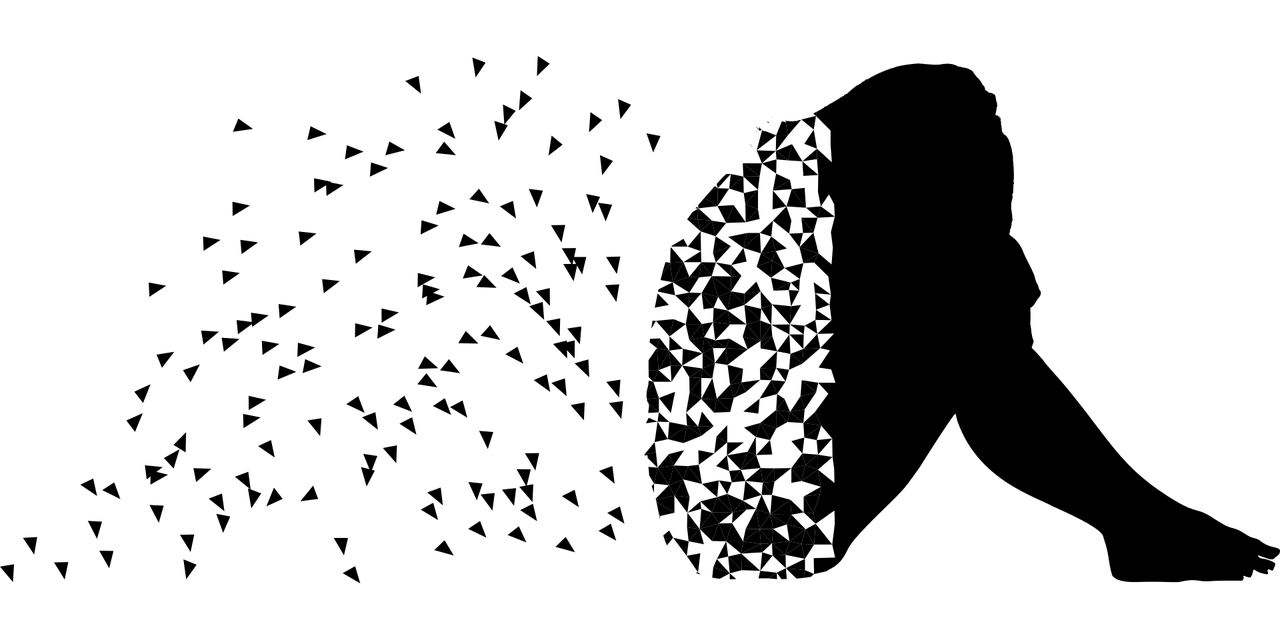
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません